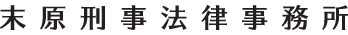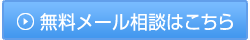刑事司法の基本構造は,ある種の勢力均衡モデルとして捉えることができます。
検察官は,被疑者・被告人の責任追及のため全力を尽くし,弁護人は,被疑者・被告人の権利利益保護のため全力を尽くし,裁判官は,そのせめぎ合いを注視しつつ,真実発見のため全力を尽くす,というような見方です。
法曹三者の存在意義は,原理的にはこの辺りにあるように思います。
もっとも,実際には,このような原理からは程遠い現実があります。
まず,責任追及を担うのが,被害者ではなく検察官なのは,被害者では冷静を保てないことや,捜査は個人ではなく組織でなければ困難であることなどが理由と考えられます。
これ自体は正当でしたが,やがて捜査機関である警察・検察は肥大化し,その組織力をもって,弁護人を圧倒するようになりました。
そして,勢力の均衡が崩れたことにより,冤罪を始めとした,数多くの問題が発生してきました。
これを是正しようと,政府は,証拠開示制度の拡充や,取調べの可視化などの法改正を進め,少しでも均衡を取り戻そうと腐心してきましたので,一昔前に比べれば,刑事司法は少しずつ改善されてきているようにも見えます。
もっとも,弁護人が,警察・検察に匹敵する能力を獲得しない限り,この問題が抜本的に解決されることはありません。
むしろ,証拠開示制度の拡充のような応急措置は,捜査機関が証拠を隠しているかもしれない,あるいは,捜査機関が保有している証拠以外の証拠があるかもしれない,などといった目を弁護人から奪い,かえって能力低下を招く危険性すらはらんでいるように思います。
とはいえ,弁護側の組織化や,捜査能力の獲得などは,一朝一夕に達成できることではなく,応急措置的な対応を続けていくしかないのか,それとも,勢力均衡モデルを機能させる画期的な制度設計があり得るのか,考え続けていくことも刑事弁護士の役割ではないかと思います。(末原)
対応地域:神奈川(横浜・川崎・相模原・横須賀・小田原・保土ヶ谷・鎌倉・藤沢・平塚・厚木・戸塚・大船・逗子・久里浜・茅ヶ崎・海老名など)及び東京