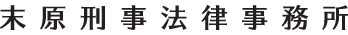法定刑
覚醒剤を所持・譲渡し・譲受け・使用した場合,1月以上10年以下の懲役に,営利目的で行った場合,1年以上20年以下の懲役または1年以上20年以下の懲役及び1万円以上500万円以下の罰金に,それぞれ処せられます(覚醒剤取締法41条の2,3,19条)。
また,覚醒剤を輸出入・製造した場合,1年以上20年以下の懲役に,営利目的で行った場合,無期もしくは3年以上20年以下の懲役または無期もしくは3年以上20年以下の懲役及び1万円以上1,000万円以下の罰金に,それぞれ処せられます(覚醒剤取締法41条)。
営利目的の場合,起訴されると裁判員裁判になります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号)。
もっとも,輸出入については,関税法違反が別途問題になり,1月以上10年以下の懲役もしくは1万円以上3,000万円以下の罰金またはその併科に処せられますので,法定刑が重い方で考えることになります(関税法109条1項,69条の11第1項1号)。
なお,所持・譲渡し・譲受け・使用行為から7年,営利目的で行った場合は10年,輸出入・製造行為から10年,営利目的で行った場合は15年で時効になります(刑事訴訟法250条2項2,3,4号)。
弁護方針
逮捕等回避
覚醒剤の場合,自首したとしても,逮捕・勾留を回避することは困難ですので,弁護士は,検察官に対し,勾留延長せず10日間で処理するよう求めていくことになります。
もっとも,事実関係を争っていたり,共犯者がいたりするような場合,勾留延長を回避することも困難といわざるを得ません(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。
起訴された場合,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。
もっとも,最近の同種前科があるなど悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。
このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。
認め事件
覚醒剤の場合,贖罪寄付,自首,依存症治療,家族など監督者の存在のアピールなどが必要になってきます。
初犯であっても,依存症治療が必要不可欠ですので,保釈後,弁護士が紹介する専門医療機関に入通院していただくことになります。
また,薬物関係者との接触を一切断つ必要がありますので,実家に戻るなどして家族等の監督に服しつつ,携帯を一旦解約するなどの措置を取る必要があります。
ご本人やご家族の更生への決意はもちろん,そのための環境がどれほどの具体策をもって整備されているかが,裁判における最も重要なポイントになります(お知らせ「情状弁護」も併せてご覧ください)。
また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該覚醒剤行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。
なお,所持や使用等の単純な事案で,かつ初犯である場合,検察官が即決裁判手続を選択することもあります。
即決手続が選択された場合,原則起訴から2週間以内に裁判が行われ,そこで判決まで下されます。
即決手続における判決には,執行猶予を付すものとされており,被告人にとってメリットが大きい手続ですが,検察官がこの手続を選択するには,弁護士の同意も必要ですので,弁護士の方から即決手続を選択するよう積極的に働きかけていくことが重要です。
否認事件
覚醒剤の場合,捜査段階では,頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。
所持や使用などの場合,現に覚醒剤が押収されていたり,尿から覚醒剤成分が検出されていたりして,犯罪成立は明らかと見られることが多いので,覚醒剤は同居人のものである,知らないうちに投与されてしまった,などといった言い分が認められるかどうかは,客観的状況を踏まえて慎重に判断する必要があります。
一方,譲渡しや譲受けなどの場合,覚醒剤の現物が存在せず,薬物関係者の供述しか存在しないことも少なくありませんので,嫌疑不十分を主張する余地があるといえます。
また,営利目的輸入などの場合,「ブラインド・ミュール」(事情を知らない運び屋)と呼ばれる問題があり,事情を知らない人間が犯行に加担させられるケースが現に存在する上,覚醒剤は,通常,輸入物の中にかなり巧妙に隠されていることもあり,輸入物の中に覚醒剤が隠されていることなど知らなかった,という言い分が認められる可能性は十分にあります。
被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。
裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。
要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。
関連条文
覚醒剤取締法19条
1 左の各号に掲げる場合の外は,何人も,覚醒剤を使用してはならない。
一 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
二 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
三 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
四 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五 法令に基いてする行為につき使用する場合
覚醒剤取締法41条
1 覚醒剤を,みだりに,本邦若しくは外国に輸入し,本邦若しくは外国から輸出し,又は製造した者(第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。)は,1年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,無期若しくは3年以上の懲役に処し,又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は,罰する。
覚醒剤取締法41条の2
1 覚醒剤を,みだりに,所持し,譲り渡し,又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は,10年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,1年以上の有期懲役に処し,又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は,罰する。
覚醒剤取締法41条の3
1 次の各号の一に該当する者は,10年以下の懲役に処する。
一 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
二 第20条第2項又は第3項(他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限)の規定に違反した者
三 第30条の6(輸入及び輸出の制限及び禁止)の規定に違反した者
四 第30条の8(製造の禁止)の規定に違反した者
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は,1年以上の有期懲役に処し,又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は,罰する。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条
1 地方裁判所は,次に掲げる事件については,次条又は第3条の2の決定があった場合を除き,この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は,裁判所法第26条の規定にかかわらず,裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
関税法69条の11
1 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。
一 麻薬及び向精神薬,大麻,あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし,政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
関税法109条
1 第69条の11第1項第1号から第6号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は,10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
刑事訴訟法250条
2 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
三 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
刑法12条
1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。
刑法15条
罰金は,1万円以上とする。ただし,これを減軽する場合においては,1万円未満に下げることができる。